兄のいたずら
 前回のエッセイ「お兄ちゃん、お姉ちゃん」では、スイスにいる姉が登場いたしました。
前回のエッセイ「お兄ちゃん、お姉ちゃん」では、スイスにいる姉が登場いたしました。
もう長い間ヨーロッパに住んでいるので、すっかりあちらに溶け込んでしまった姉です。
そんな姉のスイス人のダンナさまは、なんとも得体の知れないところがあるのです。いえ、べつに世の中の日の当たらない所で生きているとか、そんな悪い意味ではなくて、想像もつかないようなことをやってのけるという、ある種の尊敬をこめた意味なのです。
スイスに姉夫婦を訪ね、みんなでバーゼルの街を散策しているとき、義理の兄がいきなりこんな自慢話を始めました。
僕は、20代の頃に、すごいいたずらをやったことがあるんだよ。
友達が住んでいるアパートに二人で押し掛けて、そこのドア全部に、覗き穴を付けてあげたんだ。そう、あの片目で覗く、小さな穴のこと。だって、覗き穴がないと、誰が来たかわからないから、すごく不便じゃないか。
なぜだか知らないけど、このアパートには、そんな便利な物が付いてなかったんだよね。
友達も僕も、ちゃんとつなぎの服を着て、工具箱を持って、しっかりと作業員のふりをしていたんだけど、誰も僕たちを疑おうとしないんだ。そうそう、作業着の胸には、「覗き穴専門店」って刺繍も付けてたかな。
「アパートの管理人から言われて、覗き穴を付けに来ました」って僕が言うと、みんなホイホイとドアを開けてくれて、作業をさせてくれるんだよね。ほんと笑っちゃうよねぇ。
僕たちは二人とも芸術家肌だったから、穴を取り付けるのも、そりゃうまかったさ。本職とまったく変わらないくらいにね。
作業を終えて、僕たちはすっかりご満悦だったんだけど、ちょっと悪いからって、アパートの住人に白状したんだよ。実は、これは僕たちのいたずらでしたって。
そしたら、みんな怒るどころか、便利だからよかったですって、感謝してくれたんだ。だって、もともと覗き穴がない方がおかしいんだよ。
 というわけで、バーゼルを行く電車の中では、兄の武勇伝でひとしきり盛り上がったわけですが、まったくドアの覗き穴なんて、意表をつくことを考え出すものですね。しかも、考えるだけではなくて、実行にうつしてしまうとは、かなり実行力のあるお方のようです。
というわけで、バーゼルを行く電車の中では、兄の武勇伝でひとしきり盛り上がったわけですが、まったくドアの覗き穴なんて、意表をつくことを考え出すものですね。しかも、考えるだけではなくて、実行にうつしてしまうとは、かなり実行力のあるお方のようです。
それにしても、思うのです。もしこれをアメリカでやっていたら、不法侵入か器物損壊か何かの罪で、絶対に警察に突き出されていたところでしょう。
これがスイスだったから許されたのでしょうか? それとも、かなり昔だったから許されたのでしょうか? その辺は、わたしにはまったくわかりません。
けれども、よく考えてみると、みんなに便利なことをしてあげたのだから、そんなに目くじらを立てることもないのかもしれませんね。そんなことで人を捕まえる暇があったら、警察はもっと重罪犯を捕まえてください、といったところでしょうか。
収穫の季節、果樹園がたわわに実って、おいしそうな実をちょっと失敬することがありますよね。なにも農家の果樹園でなくとも、隣の家の木からちょいと実をもいで食べてみたとか、そんなことは誰にでもあることでしょう。
そういうのは、スイスではだいたい許されるそうなのです。もちろん、ごそっと失敬してはいけませんよ。それは立派な泥棒さんです。
でも、自分ですぐ食べるために、ひとつ、ふたつ拝借、というのは大丈夫なんだそうです。
なんでも、これを称して、「お口の泥棒(Mundraub)」と言うんだそうです。(もちろん、持ち主が訴え出たら、罪に問われることになりますが。)
だって、おいしそうな果実が実っていて、それをちょっと失敬して食してみるというのは、ある意味、立派な実を育んだ持ち主と自然に対する「賛美」でもありますよね。
ですから、「すばらしい物をありがとう。おいしく食べさせてもらいました」という感謝の気持ちを抱きながら失敬すれば、ひとつやふたつくらいなら許されてしかるべきことなのかもしれません。
まあ、こちらも、アメリカでは立派な窃盗罪になるんでしょうけれど。
そうやって考えてみると、何でもかんでも、規則がどうの、罪がどうのとやっていると、世の中がだんだんギシギシとしてくるのではないかとも思うのです。
アメリカの場合は、もうとっくに手遅れですけれど、日本の場合は、ギシギシに歯止めをかけることもできるんじゃないかなとも思うのですよ。
べつに果樹園から実を失敬しなさいと主張しているわけではありませんけれど。
ところで、わたしにとって初めてのスイスでは、ひどく印象に残ったことがありました。それは、スイスの南端にあるマッターホルンから、スイスの真ん中に移動するときでした。
 マッターホルンからは、ツェルマット駅始発の「氷河急行」に乗り込んだのですが、スイスの真ん中に行くためには、途中でローカル線に乗り換えなければなりませんでした。
マッターホルンからは、ツェルマット駅始発の「氷河急行」に乗り込んだのですが、スイスの真ん中に行くためには、途中でローカル線に乗り換えなければなりませんでした。
この氷河急行を降りたのが、アンデルマットという駅。そこでは、スイスの東のサンモリッツを目指す急行と、わたしたちの乗る北行きのローカル線が、ちょうど同時に発車しました。
列車が発車すると、こちらの線路はだんだんと急行から離れて行くのですが、あちらの列車の最後尾には、わたしたちに向かって懸命に手を振る親子がいるのです。それは、氷河急行の中で、食べ物を売り歩いていた母子でした。
この日は日曜日だったので、学校がお休みだったのでしょう。まだティーンエージャーにもなっていないような女のコが、お母さんと一緒に売り子をしていました。
ドイツ語の堪能な姉がサンドイッチを買うのを手伝ってくれたので、買い物はスムーズに行きましたが、わたしたちのようなアジア人の顔や、日本語や英語が飛び交う会話が、あちらの脳裏にも鮮明に残っていたのでしょう。
その異邦人の顔を列車の窓に見つけたものだから、もう一生懸命に手を振ってくれたようでした。
間もなく、わたしたちの列車は北へ、あちらは東へと分かれて行ったのですが、互いの列車が見えなくなるまで、あちらもこちらもずっと手を振り続けていたのでした。
ただそれだけのことなんです。けれども、まるでスイスの国を誇る盛大なお祭に出くわしたみたいに、今でもはっきりと覚えているのです。
そして、あの親子を思い出すと、ほっこりと明かりが灯ったように温かなものを感じるのです。


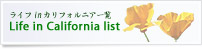
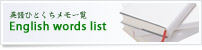
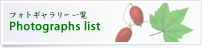

 Page Top
Page Top