慕鳥(ぼちょう)さん
前々回のエッセイ「おみやげを買いました」で、シリコンバレーの菜の花畑をご紹介いたしました。
オルソンさんのさくらんぼの果樹園で、一面に咲いていたものです。
そのとき、あんなにたくさんの菜の花を見て、ある詩を思い出していました。
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
いちめんのなのはな
かすかなるむぎぶえ
いちめんのなのはな
第一連はこんな風な、とっても印象深い詩。
誰にでもわかる平易な言葉が、よけいに菜の花の迫力を伝えています。
これは、詩人・山村慕鳥(やまむらぼちょう)の作。大正4年(1915年)に発表された、「風景」という題名の詩です。
一行だけ挿入された「かすかなるむぎぶえ」は、第二連では「ひばりのおしゃべり」、第三連では「やめるはひるのつき」と替えられています。
「やめるはひるのつき」とは、「病めるは昼の月」のことでしょうか。床に臥せって見上げる、昼間のぼんやりとした月なのかもしれません。とすると、「いちめんのなのはな」とは、心の中に咲く花なのでしょうか。
この山村慕鳥という名を聞いて最初に思い出すのが、代表作ともいえる「雲」。誰しも一度は聞いたことがあるかもしれませんね。
おうい雲よ
ゆうゆうと
馬鹿にのんきそうぢやないか
どこまでゆくんだ
ずつと磐城平(いはきたいら)の方までゆくんか
(仮名づかいと送り仮名は、底本のとおりです)
この磐城平の方角には、慕鳥の友である詩人・三野混沌が住んでいて、孤独な開墾生活を送っていました。
慕鳥に勧められてキリスト者となった混沌は、この雲の行き先は俺のところだと、妻せいに語っていたそうです。
初出時は、「友らを思ふ」という名のこの詩。
雲を詠んでいるようで、実は、親しい友を詠んでいるのですね。
わたしが慕鳥と出会ったのは、小学生の頃。父の本棚にあった文庫本を覗いてみたのが縁でした。
ひとつひとつ読んでいくと、小学生のわたしにもわかるやさしい言葉遣い。詩人にありがちな小難しい表現もなく、心にすっと入ってくるような、飾りっけのない詩。どことなく土くささもあり、自然を感じます。
そのとき、「風景」や「雲」とともに、大好きになった詩がこれです。
驚くなかれ、名づけて「野糞先生」。ユーモラスな詩なのです。
かふもりが一本
地べたにつき刺されて
たつてゐる
だあれもゐない
どこかで
雲雀(ひばり)が鳴いてゐる
ほんとにだれもゐないのか
首を廻してみると
ゐた、ゐた
いいところをみつけたもんだな
すぐ土手下の
あの新緑の
こんもりした潅木のかげだよ
ぐるりと尻をまくつて
しやがんで
こつちをみてゐる
いやはや、最初にこれを読んだときは、大笑いしたものでした。そして、こんなもんが詩になるんだと、仰天もしました。
でも、大人になって、もう一度読み返すと、なんとも美しい詩だと思うのです。優しい新緑の風景の中にも、たくましい人の営みを感じる。何の見栄もない、人間賛歌ともいえる素朴な詩。
詩って、本来、こんな風でなくっちゃいけないのかもしれませんね。眉間にしわを寄せるのではなく、肌からすっと体の中に入っていくようなもの。
山村慕鳥さん。彼は、明治17年(1884年)、群馬県の農村で生まれました。
一時期、伯父である神官に育てられますが、父母を追って千葉県佐倉へ移ります。両親と同居したのもつかの間、わずか12歳で家を出て、陸軍御用商人、活版職工、紙屋、ブリキ屋と職を転々とし、16歳で生まれ故郷に戻ります。
年齢を偽り、尋常小学校の臨時雇いとなったり、教会の英語夜間学校に通ったり、伝道学校に入学したりと、二十歳までに、いろんな人生経験を積むのです。
その後、伝道師として教会に赴任するかたわら、詩を書くようになり、27歳のときに自由詩社の同人となって、筆名を山村慕鳥とします。
ボードレールに心酔し、フランス語を学んでみたり、友・三野混沌の開墾生活を訪ね、自分も野菜づくりを始めたりと、いろんなことに興味を抱く慕鳥でしたが、35歳のときに結核におかされ、わずか40歳で他界してしまうのです。
子供の頃は、まったく頓着しませんでしたが、慕鳥さんの優しさには、キリスト者としてのあらゆる命への愛情が表れているのかもしれません。
短く綴られる言葉の中にも、その優しさが余すところなく出ています。
この「桜」という詩にも。
さくらだといふ
春だといふ
一寸、お待ち
どこかに
泣いてる人もあらうに
追記:残念なことに、今では、山村慕鳥の詩集は、ほとんど店頭には見当たりません。
唯一見つけたのが、日本図書センター発行の『雲』。「愛蔵版詩集シリーズ」と名づけられたもので、山村慕鳥の他に、慕鳥の詩人仲間である萩原朔太郎、室生犀星らが取り上げられています。
ご紹介した詩の中で、「風景」は『雲』の中にはありませんが、「雲」、「野糞先生」、「桜」が収められています。
ある日卒倒したほどの酷評を受けたこともある慕鳥。詩集『雲』は、そんな暗い時代を抜け、守るべき子供も生まれ、余分なものを全部削ぎ落としたような表現で編まれています。
『雲』の序で、慕鳥はこう書いています。「詩が書けなくなればなるほど、いよいよ、詩人は詩人になる。だんだんと詩が下手になるので、自分はうれしくてたまらない。」
慕鳥が『雲』の校正を終えたのは、病の床の中。数日後没した彼は、刊行された形を目にしていません。
その頃、結核といえば死の病で、志半ばにして没した文壇の士もたくさんいたのですね。

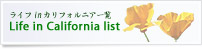
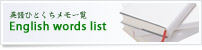
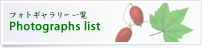

 Page Top
Page Top