もってこ〜い、長崎くんち!
<エッセイ その205>
ようやく夏の暑さが去ったと思えば、急に朝晩が寒くなってきましたね。
そんな10月の話題は、有名な秋のお祭り、『長崎くんち』です。

長崎くんちは、毎年10月7日〜9日の3日間に開かれ、諏訪神社(すわじんじゃ)の氏子である町々が神さまに演し物(だしもの)を奉納するというもの。「お諏訪さん」の秋季大祭であり、神さまの加護に厚く感謝し、さらなる加護を願って、最高のおもてなしをする、というお祭りです。
長崎近郊では、神社の秋祭りは「くんち」と親しまれ、諏訪神社だけではなく、周辺の街でも開かれます。例えば、伝統的な浮立を奉納する『矢上くんち』や、狐に扮した若者が竹の上で曲芸をする「竹ン芸(たけんげい)」で知られる『若宮くんち』と、長崎市周辺だけでも40ほどのくんちがあります。
けれども、秋のくんちといえば、国の重要無形民俗文化財にも指定される、お諏訪さんの祭りが一番有名でしょうか。
コロナ禍で3年間延期となっていたので、今年は、待ちに待った4年ぶりの開催となりました。7、8日は土日、9日は祝日と、見学者にとっては最高のタイミングでもあり、日本各地から見物に来られた方も多かったことでしょう。
長崎くんちに縁のない方でも、「龍踊り(じゃおどり)」や「コッコデショ」という名は耳にしたことがあると思いますが、毎年、神さまに奉納する演し物は変わります。

くんちに参加する町は「踊町(おどりちょう)」と呼ばれ、7年に一回だけ奉納踊(ほうのうおどり)の当番がやってきます。
各踊町は独自の演し物の伝統を引き継いでいて、ある町は華やかな踊りを披露し、ある町は曳き物(ひきもの)と呼ばれる船型の山車を曳き回す、と(神さまが)見ていて飽きない趣向が凝らされています。
毎年くんちには、6つか7つの踊町が参加しますが、当番は7年に一度しか回ってこないので、すべての踊町の演し物を見ようとすると、7年間長崎に通わなければなりません!
各町が思い思いの諸芸を奉納するのは、寛永11年(1634年)から続く伝統のスタイル。当初は、こちらの舞踊のように、芸妓衆(げいこし)が踊りを披露していましたが、だんだんと華やかになってきて、今ではバラエティーに富んでいます。
(写真は、丸山町の長崎検番が奉納する長唄『唐人共祝崎陽祭(とうじんともにいわう きようのおまつり)』。「崎陽(きよう)」とは長崎のことで、芸妓と唐人さんが酒の席でうかれる様子を舞う、別名『うかれ唐人』)

わたし自身、これまで何回か長崎くんちを見物したことはありますが、いまだ本家の諏訪神社で奉納踊を見たことはありません。ひとつに、ここの観覧券は高倍率で手に入りにくいし、朝7時からの奉納とは、あまりにも早すぎる!
そこで、今年は、7日の前日(まえび:くんち初日)午後5時から中央公園で開かれる「くんちの夕べ」を楽しみました。(チケットはネット購入できますが、発売スタートと同時にアクセスして、かろうじて良い席を入手しました)
今年は、久しぶりのくんち見物でもあり、これまでとは違った印象を持ったのでした。
それは、長崎くんちは、老若男女すべての人たちの祭りであるということ。
祭りといえば、ともすれば「男だけ」とか「女だけ」と制限がある場合も多いです。けれども、長崎くんちの参加者は、男の子も女の子も、よちよち歩きの幼児からティーンエージャーまで、子供の頃から大事な役割を持っています。
曳き物や担ぎ物(かつぎもの)となると、鍛えられた男性陣の力は必須ですし、長年の経験者が持つ技と勘も不可欠です。踊りを披露するにも、あでやかな若い娘さんばかりではなく、ベテランの踊り手も唸るようなうまさを発揮します。
たとえば、上の写真は今年の一番町、桶屋町(おけやまち)の『本踊(ほんおどり)』のオープニング。
この町のシンボルともなる傘鉾(かさぼこ)には、江戸時代のカラクリ仕掛けの白象とオランダ人の人形が飾られます(市指定の有形文化財)。この象さんに呼応するかのように、女の子たちが引いているのは、かわいらしい子象さん。
以前もご紹介しましたが、長崎は日本で初めて象さんが上陸した地。そんな歴史をほっこりと物語る一幕です。(以前は、江戸城の徳川吉宗公に上覧された象さんをご紹介しましたが、そのあとオランダから連れて来られた象さんは、「もういいよ」と江戸から断られ、すごすごとオランダに帰されたというエピソードがあるとか!)
そして、子供の参加者といえば、船大工町(ふなだいくまち)の『川船(かわふね)』。その昔、船大工町には、たくさんの船大工が住み、船着場もあったそうですが、こちらは川で漁をする船を再現。
長崎市内には、漁をするほど大きな川はありませんが、立派な御座船を川に浮かべ、勢いよく泳ぐ鯉をつかまえるという設定です。まわりの根曳き衆(ねびきしゅう)は、川面にうねる波を表します。

船頭の大役を務めるのは、8歳の男の子。もともとは、こちらの悠真(ゆうま)くんのお兄ちゃんが船頭を務める予定でしたが、コロナ禍で3年延期となったことで、悠真くんに大役が回ってきたそう(料亭 一力(いちりき)の女将さん情報)。
お父さんの光安健一郎さんは、39年前に7歳で船頭を務めた経験もあり、そのお父さんの網を使って、夏の間、悠真くんは網を打ち、鯉七匹を一網打尽にする猛練習を積んできたそう(写真では、悠真くんの足を支えているのがお父さん)。
くんちに参加することは、7年に一度の誉ですが、今回は10年も待ちました。その間、出られなくなった子供たち、急にピンチヒッターとなった子供たち、振り付けを変更して参加できた子供たちと、いろんなドラマがあったようです。
各踊町にとっては、当番が回ってくるタイミングも大事な人生設計に組まれますが、コロナ禍は、まさにプランできない番狂わせでした。

そして、船を曳く「根曳き衆(ねびきしゅう)」の方々。最初は、お母さんの手に引かれて曳き物の先導役「先曳き(さきびき)」となり、小学生になると、お囃子担当となって船に乗り込む。長じては、根曳きとして力強く船を曳き、船回しを披露する。経験を積むと、責任者として采(さい)を振り、最終的には、長采(ながざい)となって総指揮を執る。
そんな風に、小さい時から祭りに親しみ、大人になっても参加できることに誇りを持つ。現役を引退しても、サポート役にまわって現役を支え続ける。各踊町には、そういった代々のバトンの受け渡しがあるようです。
一方、長崎くんちの面白さは、ストーリー性にもあります。

昔から有名な演し物に、『阿蘭陀万歳(オランダまんざい)』というのがあります。長崎に漂着したオランダ人が、生計を立てるために万才を身に付け、家々をまわって新年を寿ぐ(ことほぐ)という設定です。
もともとは、貫禄のある万蔵(まんぞう)とチョコチョコとコミカルに動きまわる才蔵(さいぞう)の二人で行う踊りですが、今年の栄町(さかえまち)の阿蘭陀万歳には、四人が登場。途中、いつのまにか才蔵二人が入れ替わって、あれ? と顔を見合わすシーンがあったり、かすかに教会の鐘の音が聞こえてきて、故郷オランダを想って涙するひとコマを加えたりと、新しい演出になっています。
オランダといえば、鎖国時代の長崎にふさわしい演目と思えますが、実は、初演は東京だったそう。昭和9年、長崎の国際産業観光博覧会で披露しようと、花柳流のお師匠さんが踊ったのが長崎初演。昭和26年、料亭 一力のある新橋町(今の諏訪町)が、初めてくんちの演し物として披露しました。
昭和31年以降、こちら栄町(当時は眼鏡橋町)の演し物ともなっていて、唐子(からこ)、町娘、オランダ人が登場し、長崎の「和華蘭(わからん)文化」を体現しています。

阿蘭陀万歳を踊るには、花柳流の名取(なとり)でないといけないそうですが、黄色い才蔵さんは、18歳の高校3年生、久原一花(くばらいちか)さん。受験勉強をしながらの大役でしたが、キビキビとした動きに豊かな表情と、例年よりも活きいきとした阿蘭陀万歳となりました。
オランダ人が主役の舞踊ですが、三味線や太鼓のお囃子に加えて、弓を使う胡弓(こきゅう)も登場。胡弓の音色がまた、哀愁を感じさせるのでした。
ストーリー性といえば、本石灰町(もとしっくいまち)の『御朱印船(ごしゅいんせん)』は、また格別です。
豊臣秀吉が朱印船貿易の朱印状を最初に与えたひとり、豪商の荒木宗太郎が主役。宗太郎がヴェトナムの王家からお嫁さんを連れ帰り、豪華絢爛のお輿入れが行われた様子を再現しています。
くんちの踊場では、船が長崎港に近づき、宗太郎がお嫁さんのアニオーさんに「あれが長崎だよ」と示す様子や、上陸したアニオーさんのあとに何人も従者が続く「アニオー行列」を再現。実際にヴェトナムから来られた方々も、アオザイを身に付けて従者として登場します。

くんちの曳き物ということで、御朱印船も「船回し」を披露。当時の航海は、風まかせの命がけの冒険です。激しい船回しは、大海原の波に揉まれる様子を、静かな船回しは、風が止み穏やかな凪(なぎ)を表します。
御朱印船は、くんちの演し物でも最大級。高さ6メートル、重さ5トンの船を18人で動かします。そのうちの16人が新人という今年は、厳しい猛練習が続いたそうですが、静と動の対比が際立つ、見事な船回しでした。船に乗り込んだ子供たちのパラパラ、キャンキャン、ドラや大太鼓のお囃子が、統率の取れたリズムで演出を盛り上げるのです。
この時のお輿入れのような豪華絢爛さは、「アニオー行列のごたる(アニオー行列のようだ)」と街で語り継がれたそうで、当の宗太郎とアニオーさんは、仲良く大音寺の荒木家の墓に眠っていらっしゃるとか。アニオーさんがヴェトナムから持参した鏡は、今でも歴史文化博物館に保存されているそうです。

そして、長崎くんちのユニークな演し物といえば、万屋町(よろずやまち)の『鯨の潮吹き(くじらのしおふき)』があります。
くんちの演し物には、『龍踊り』や『川船』のように複数の踊町が披露するものもありますが、万屋町の『鯨の潮吹き』と樺島町(かばしままち)の『コッコデショ(神輿のような太鼓山)』は、ここだけの演し物となっています。ゆえに、7年に一回しか見られません!
そして、この二つは、くんちが始まった頃からの演し物で、『鯨の潮吹き』の初奉納が安永7年(1778年)、『コッコデショ』が寛政11年(1799年)と、江戸時代から引き継がれた伝統を誇ります。二つとも、シーボルトの日本研究の集大成『日本』で海外に紹介されたという、歴史的な演し物です。
『鯨の潮吹き』は、かつて長崎の海で盛んだった捕鯨を表します。大海原を悠々と泳ぐセミクジラを捕鯨船5隻で捕らえるという設定。今となっては、海外から非難を受けそうな演目ではありますが、捕鯨は、長崎の歴史の大事なひとコマ。(写真は、栄町(昔の袋町)に生まれた日本画家、中山文孝(なかやまよしたか、1888-1969)氏が「無全」という名で描いた『鯨の潮吹き』。中山氏は、カステラの老舗・福砂屋(ふくさや)の黄色い包装紙のデザインでも有名。所蔵:料亭 一力)
くんちの踊場では、セミクジラは数メートルの潮を吹き上げ、「ヨッシリヨイサ!」の掛け声とともに2トンの黒い巨体を回し、鯨と戦う厳しさを表します。くんち初日には、鯨は捕まっていませんが、最終日になると、鯨には網がかかり、納屋船の屋根には冬の漁を表す雪とツララが現れます。脂の乗った冬のセミクジラは、まさに最高級品だったとか。
鯨は、竹で緻密に骨格を組み、黒いサテンで覆います。毎回、新調されるそうですが、根曳き衆の指が入り込まないように竹は隙間なく組まれ、それゆえに、水に濡れたサテンの鯨はツルツルとすべり、えらく回しにくいとか。

船頭さん10人は、子供たちの役割。親船頭を務めるのは、10歳の浅野正宗くん。コロナ禍の延期で大役が回ってきたそうですが、正宗くんの「ヨイヤーサー、ヨイヤーサー」という掛け声は会場じゅうに響き渡り、大人たちの『祝い唄(祝いめでた)』に勢いをつけます。
船頭さんが身につける衣装がまた、特筆すべきものなのです。写真ではわかりにくいですが、衣装は「長崎刺繍(ながさきししゅう)」が施された豪華絢爛なもの。長崎刺繍とは、金糸や銀糸の模様の中に綿を入れて立体的に刺繍するもので、2着を新調するにも6年がかりだったそう。
正面からは見えませんが、正宗くんの背中には、立体的な黒い鯨が、仲間の背には、伊勢海老が施されています。

万屋町の町印となる傘鉾(かさぼこ)にも、『魚づくし』と呼ばれる垂(たれ)を用いていて、こちらは、16種29匹の魚を長崎刺繍で再現。10年前に200年ぶりに新調されたもので、製作には11年かかったとのこと。市の有形文化財にも指定されています。
現在、長崎刺繍の継承者は、嘉勢照太(かせてるた)氏おひとりだそうですが、大切な伝統を受け継ごうと、お弟子さんが何人かいらっしゃって、みなさんで協力してくんちの衣装や飾り物を製作されています。
万屋町の傘鉾には、「福」を呼ぶ工夫も。
こちらに見えるように、傘鉾の裏側、ちょうど垂が重なる部分には、フグ(ふく、福)が刺繍されています。普段は隠れていて、傘鉾がクルクルと勢いよく回ると、フグが姿を現し、これを見かけた人には福が訪れるというもの。

長崎刺繍といえば、上でもご紹介した船大工町の『川船』。船頭さんが登場する際は、こちらの金糸の伊勢海老の衣装を身につけています。
皆で踊場に整列して、ごあいさつをしたあとは、船頭さんはズッキャンキャン(肩車)されて船を下り、衣装替えをして、軽快な船頭さんの姿となって網を打ちます。
くんちの衣装といえば、根曳き衆や采振りの着物は、足さばきが良いように「正絹ちりめん」でできています。祭りには、綿の法被(はっぴ)というイメージもありますが、長崎の祭りには、いなせに絹をまといます。
根曳き衆の着物には、各踊町のテーマが染め抜かれ、川船には大波に鯉、御朱印船にはアニオーさんの祖国ヴェトナムの国鳥トキと、カラフルな衣装を見るのも楽しみのひとつです。
お囃子や謡(うたい)のみなさんも紋付の正装を身につけ、石畳の踊場では、雨が降ろうと、何も敷かずに着物のまま座ります。それが、長崎の人間の心意気! というわけです。
心意気の表れとして、演し物や衣装、小道具や楽器と、贅を尽くすのが「くんち」の常識ではありますが、町のシンボルともなる傘鉾(かさぼこ)にも凝った細工を施します。

通常、くんちの費用は町全体で負担しますが、特筆すべきは、上でもご紹介した『阿蘭陀万歳』を奉納する栄町の傘鉾。
こちらは、旧家が一軒で負担する「一手持ち」だとか。栄町は、酒屋町、袋町、本紺屋町(もとこうやまち)の三町が合併してできた町で、酒屋町で生まれた明治期の実業家、松田源五郎一族の一手持ちということです。
源五郎さんは、金融業を立ち上げ、のちの国立十八銀行に発展させると同時に、幅広い分野の企業経営に携わった人物。市議会、県議会、そして衆議院でも議員を務めました。人から認められる人格者でなければ、一手持ちにはなれないそうで、長崎には「傘鉾ば持つごとならんばのぉ(傘鉾を持てるようにならなきゃね)」という言葉があるのだとか。
酒屋町だった頃には、盃(さかずき)を頂く傘鉾でしたが、今は、源氏物語を題材とした「貝合わせ」4枚と紅葉が飾られます。垂は前日(まえび)には白、後日(あとび)には紫と、粋に色を替えるそう。
貝合わせといえば、母が源氏物語の勉強会の仲間と、松田家の若奥さまに「お雛さまを見にいらっしゃい」と招待されたことがありました。座敷いっぱいに飾られる立派な雛壇にも驚いたそうですが、それ以上に、源氏物語の有名な場面を描いた美しい貝合わせに心奪われた、と語っていました。
まさに長崎の旧家の懐の深さの表れですが、雛人形にすら縁のなかったわたしにとっては、貝合わせとは、京の貴人のお遊びみたいと、脳裏に深く刻まれたエピソードとなりました。
というわけで、なんとも独善に満ちた長崎くんちの印象をつづってみました。

まだまだ書き足りないことはありますが、表題の『もってこ〜い、長崎くんち!』について、ひとこと。
ご存じの方も多いとは思いますが、くんちの踊場でアンコールをお願いするには、「もってこ〜い、もってこい」と声をかけます。奉納踊が始まる前には、観客も掛け声を練習します。
踊場では、白トッポと呼ばれる白法被の男たちが、あとどれくらいアンコールできるかと、総指揮者の長采の顔色をうかがいながら掛け声をかけるのです。
「もってこ〜い、もってこい」は、力強い根曳き衆の曳き物や担ぎ物に使われ、あでやかな舞には、「所望(しょもう)やれ」と声をかけます。反対に、気に入らないと「もっていけ〜」との罵声もあるそうですが、いまだ耳にしたことはありません。(写真は、桶屋町の『本踊り』より、藤間流の門下生による長唄『諏訪祭紅葉錦絵(すわまつり もみじのにしきえ)』)
いつか秋の長崎に足を伸ばす機会がありましたら、くんち見物を予定に組むことをお勧めいたします!
<歴史のこぼれ話>
そもそも、長崎近郊に広まる「くんち」という名前は、中国や香港、台湾、ヴェトナムに伝わる「重陽(ちょうよう)の節句」からきている、という説があるそうです。旧暦9月9日、先祖の墓参りをして、邪気を払い、長寿を願う節句だそうで、日本では「くんち(9日)」として秋祭りになったとか。
上ではご紹介しませんでしたが、くんちの期間中、諏訪神社の「諏訪」「森崎」「住吉」の三柱の神さまが神輿三基で元船町の御旅所に往復されるという「お下り」「お上り」も行われます。こちらは、10月7日(前日)と9日(後日)に行われ、天狗や神官、稚児さんと昔の装束に身を包んだ方々が街を練り歩きます。神輿三基が諏訪神社の急な階段を駆け抜ける様子も、迫力に満ちあふれ人気を誇ります。
長崎の街は、豊臣秀吉の時代に、大村純忠によってローマ・カトリックのイエズス会に寄進されました。イエズス会の領地としてキリシタンが激増しましたが、その反動でキリスト教の禁教令が発布され、教会関係者や信徒は弾圧され、教会の代わりに寺社が保護されました。天領となった長崎のくんちは、キリスト教を庶民の心から払拭する手立てとして、お上に利用された一面もあるのでしょう。
江戸時代には幕府の援助を受け、諏訪神社は20余名の能役者を抱え、能を催していたそうで、歌舞の伝統が街じゅうに広く浸透していたことも、くんちの発展に寄与したのではないでしょうか。
今年、長崎検番のある丸山町が奉納した『うかれ唐人』ですが、こちらは、引田屋花月楼(今の料亭 花月)で丁重にもてなしてくれた遊女へのお礼として、唐人が気分よく舞を披露した、という設定です。
丸山遊郭の女性たちは、教養も高く、芸事にも秀で、そんなレディーたちを大切にした唐人さんたちは、文化人であると好感を持たれたそう。「色もほんのり良かばってん チクライ チクライ カーラリ フーラリミョー」といった和製中国語の歌詞にも、長崎の人々の唐人さんへの親しみが込められているようです。
おくんちの演し物には、踊場で奉納するだけではなく、「庭先回り(にわさきまわり)」でお得意さんを回るという大事な役割もあります。街をブラブラしていたら、好きな演し物に出くわした。そんな偶然もまた、くんちの楽しみではありますね。















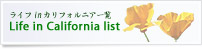
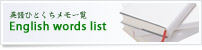
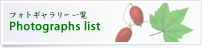

 Page Top
Page Top