福岡の住吉神社〜リニューアルした能楽殿
<エッセイ その208>

新しい年が明けたと思ったら、まもなく立春です。
有名な太宰府天満宮(だざいふ てんまんぐう)の『飛梅(とびうめ)』もほころび、辺りは春隣(はるとなり)のかぐわしさ。
飛梅は、京都より左遷された菅原道真公を慕って、一夜のうちに都から太宰府に飛んできたと伝わる古木。「学問の神様」にお参りする受験生たちを温かく迎えているのです。
さて、前回のエッセイでは、福岡と日本最古の書物『古事記(こじき、ふることふみ)』の意外な関係をご紹介いたしました。
日本の国を造ったとされる伊邪那岐命(イザナギノミコト)と伊邪那美命(イザナミノミコト)の二神が、黄泉の国(よみのくに)で壮絶な再会を果たしたあと、イザナギノミコトが禊(みそぎ)をしようと竺紫(つくし)へやって来て、そこで神々が生まれた、というお話。
この禊の地「竺紫の日向の橘の小戸の阿波岐原(つくしの ひむかの たちばなの おどの あはきはら)」とは、いったいどこなのか?
これには諸説あって、宮崎市の阿波岐原町(あわぎがはらちょう)にある江田神社(えだじんじゃ)の辺りという説もあるそう。
太平洋を臨む有名リゾート、フェニックス・シーガイア・リゾートに隣接し、広大な黒松の森に抱かれるところ(写真では右奥の森に江田神社が隠されます)。
宮崎というと、高千穂(たかちほ)をはじめとして、県全体に神話のふるさとというイメージがあり、なかなか説得力がありますよね。
が、前回ご紹介したのは、竺紫というのは「筑紫」、つまり福岡県ではないかと考えられる、というお話でした。なぜなれば、福岡には、イザナギが禊をされた際にお生まれになった神々を祀る神社がいくつも存在するから。
最初に身の汚れから生まれた神と、その禍を直そうと生まれ出た神々を祀る警固神社(けごじんじゃ、福岡市中央区天神)。
三柱の海の神、綿津見神(ワタツミノカミ)を祀る志賀海神社(しかうみじんじゃ、福岡市東区志賀島)。

そして、住吉三神と親しまれる、三柱の筒之男命(ツツノヲノミコト)を祀る筑前国一ノ宮 住吉神社(ちくぜんのくにいちのみや すみよしじんじゃ、福岡市博多区住吉)。
とくに住吉神社に関しては、鎌倉時代の僧侶、顕昭(けんしょう)が著した歌学書『袖中抄(しゅうちゅうしょう)』にこのような記述がありました。
「住吉の神々は、もともと筑前(福岡)小戸にあり、荒御魂(あらみたま)は常にここにいらっしゃる。今は、和御魂(にぎみたま)は摂津墨江(せっつすみのえ、大阪市)にいらっしゃるが、神功皇后がこちらに分祀なさったのだ」と。
福岡といえば、常に変化し続け、あまり歴史を感じさせない街ですが、実は古事記にも深い関わりを持っている。前回は、そんなことをご紹介したのでした。
というわけで、今日は、住吉三神のいらっしゃる筑前国一ノ宮 住吉神社にフォーカスいたしましょう。

実は、この住吉の辺りは、我が家にとっては愛着のある地域で、それは、住吉神社の斜め前に住吉酒販という酒屋さんがあるから。
日本全国から仕入れた日本酒やヨーロッパのワインと、日本人客だけではなく、韓国からいらした観光客も訪れる酒屋さん。飲み屋街の中洲(なかす)からは川向こうにあり、博多駅にもほど近い便利な立地。今は整然と区画整理されていますが、昔は、問屋や商家の集まる賑やかな地区だったのでしょう。
我が家にとっては「酒」のイメージの強い住吉ですが、あるとき、住吉神社の境内を散策したときから、この神社の魅力にひき込まれたのでした。
なんといっても、都会にありながら境内が広い。境内には、住吉神社本殿だけではなく、三日恵比寿神社や荒熊・白髭稲荷神社など、たくさんの神々が祀られます。
それぞれの建物は静かな木立や池に囲まれ、どの季節に散策するにも最適なところ。
本殿は、元和9年(1623年)初代福岡藩主 黒田長政によって再建されたもの。戦乱によって荒廃した神社を長政が再興し、現在、本殿は国の重要文化財に指定されています。

この住吉神社にあるのが、「西日本随一」とうたわれた能楽殿。
大正時代に警固神社の能楽堂が老朽化したため、昭和10年(1935年)能楽愛好家の間で、住吉神社の境内に能楽堂を建設しようという計画が生まれます。昭和13年(1938年)に落成し、その後、住吉神社に寄贈されます。激しい太平洋戦争の戦火も、奇跡的に免れました。
近年は老朽化対策と耐震補強、そして増築部分を取り払うために改修工事が行われ、2年の修復作業ののち、昨年10月に柿(こけら)落としを迎えました。
前回のエッセイでも触れていますが、わたしがこの能楽殿に入ったのは、七五三を控える11月中旬。郷土史研究家 清田進氏が主催する『那国王の教室』の勉強会が、美しく修復された能楽殿で開かれたのでした。
前月の柿落としのイベントには役所関係の方々が列席されたそうなので、一般市民でゆっくりと座ったのは、わたし達が初めてだったそう!

そんなわたし達をお迎えくださったのは、住吉神社宮司・横田昌和氏と禰宜・桐田篤史氏のお二人。
この日は、桐田氏(写真)に能楽殿の歴史や内部構造についてご説明いただきました。
なんでも、戦前の木造の能楽殿は、全国的にもまれで、東京都杉並区にある杉並能楽堂など数えるほどだそう。
杉並能楽堂は、明治43年(1910年)本郷弓町(現・文京区本郷)に建てられ、昭和4年(1929年)に和田堀内村(現・杉並区和田)に移築再建。杉並区の有形文化財にも指定されています。
江戸時代には幕府や各藩に保護されていた能や狂言は、明治期になると政府の庇護を失います。そんな背景があって、明治期以降、なかなか能楽堂が建てられることはなかったそう。
こちらの住吉神社能楽殿は、杉並能楽堂よりもずっと規模が大きく、劇場のようにゆったりとした形をしています。洋風建築技術を取り入れるなど、建築史上きわめて貴重な建造物であり、福岡市の有形文化財にも指定されています。

中に入ると、その広さに圧倒されます。外から見るとわかりにくいのですが、こぢんまりとした能楽堂ではなく、まさに「劇場」という名がぴったりな和洋折衷の広々としたスペース。
天井は高く、ゆったりと空間を見渡せます。ゴザを敷いた板張りの桟敷席は、上段・中段・下段に分かれます。床は少し前に傾斜し、前列の人が気にならないように工夫されています。
珍しいのは、舞台の右手に貴賓席が設けられていること。
公演中は、貴賓席に御簾(みす)が下げられ、どなたが観劇されているのか、一般の観客にはわからないようになっていたとか(舞台右手の黄色い御簾の向こうが貴賓席)。
客席の右端に小さな階段があって、一旦そこを下り、細い階段を上って貴賓席に行けるようになっています。神社の能楽殿ということもあり、皇族の方がいらっしゃることを想定されたのでしょうか。

そして、肝心の能舞台。
橋掛(はしがかり)は長く立派で、近年に建てられた大規模な能舞台にも引けを取りません。
橋掛とは、静かに登場を待つ鏡の間から本舞台へと向かう通路ではありますが、あの世から現世へと亡霊が訪れたり、遠くから旅人が訪ねて来たりと、時空を超えた演出を手助けするもの。ここには存在しない設定の演者が控えることもあり、単なる通路ではない奥深さがあります。
舞台を正面から見ると、美しい絵が目に飛び込みます。背面の「老松」と側面の「若竹」は、地元・筑紫郡住吉村(現・博多区住吉)が輩出した日本画家、水上泰生(みずかみたいせい)画伯が描かれたものだそうです。
水上画伯は、明治から昭和にかけて活躍された日本画家で、とくに背面の老松は構図も美しく、躍動感を感じます。花鳥画の中でも「鯉」がお得意だったそうで、一本の松にも風にゆらぐ枝葉の様子や、宿った命の力強さを見て取れるのです。
背面の鏡板の老松は、鏡に映る松の姿を表すそうですが、松とは、神々が人の前に現れるときに依り憑く(よりつく)もの。
能は、芸であると同時に、神事でもあります。神聖な舞台空間を創り出す上で、松の絵は不可欠な要素なのです。
舞台は総檜づくりで、音質は柔らかく、音響の良さに一役買っています。
そうなんです、こちらの能楽殿は、音響の良さも特筆すべき点でしょうか。
舞台奥の天井は斜めに張られていて、客席に向かって音が響くように工夫されています。
舞台の裏手と天井裏には大きな空間が設けられていて、音の反響を助長します。
なんでも、音はこういった空間に一旦こもって、そのあと前に押し出されてくるような構造になっているとか。
この音の響きに関して、「お唄が渦を巻く」と表現する方もいらっしゃったそう。
床下にも大きな空間があって、地面には大きな甕(かめ)が何個も埋められています。
こちらの写真は、翌月(2023年12月)に開かれた能楽殿見学会に参加した友人が撮影したもので、床下にはゆったりとした空間があり、陶器の甕が何個も埋められている様子が見えたそう。
大きなものは8個(現存7個)、舞台と橋掛を合わせて全体で13個の甕が埋められていて、各々の甕は、音の響きを考慮してあちらこちらの方向に向けられています。
能舞台では、笛や太鼓のお囃子や謡(うたい)に加えて、足で舞台を踏む「足拍子」も多用されます。そんな音全体がより美しく共鳴するようにと、古来、舞台下には甕を埋めて共鳴装置としました。甕はそれぞれ埋める方向を違えて、より良い音響に微調整するのです。
こういったさまざまな工夫は、古くから能舞台に施されているものですが、こちらの能楽殿は、とくに演者の方々にも音響効果が良いと評されているのです。

舞台の上に目をやると、屋根は、檜皮葺(ひわぶき:ヒノキの樹皮で葺く工法)。
橋掛の屋根は、杉材を使った柿葺(こけらぶき:木の薄板を何重にも葺く工法)。
通常、舞台屋根は柿葺が一般的だそうで、そこから劇場の初興行「こけら落とし」という言葉が生まれたそうです。が、こちらの舞台屋根は、ひとつずつヒノキの皮を重ねた檜皮葺とのこと。
そして、舞台屋根を支える梁には、透かし彫りの蟇股(かえるまた)。多分に装飾の意味合いが強い細工ですが、細部にまでこだわりが感じられます。
こちらは、壁面に用いた懸魚(げぎょ)という装飾で、魚をつるした形を表します。
もともとは屋根の棟木を隠すために施されたものですが、装飾としてさまざまな文様が派生していきました。
木造建築は火災に弱いので、水に縁のある魚をモチーフにして、「火除け」のおまじないとしたそうです。
こちらはごくシンプルに簡略化された文様ですが、激しい戦火もくぐり抜けたという経緯は、懸魚のおまじないのおかげでしょうか。

舞台の足下に目をやると、ぐるりと舞台を囲むのは白洲(しらす)。
白い玉砂利が敷かれた部分は、日常と神聖な場である舞台を隔てる「結界(けっかい)」を意味します。
それと同時に、実用性もあって、天窓から射し込んだ日の光が玉砂利に反射し舞台を照らすという、間接照明の役割もあるのです。これによって、シテの感情表現が際立つそうです。
というわけで、美しく改修された住吉神社の能楽殿。これからさまざまな演目が上演され、名を馳せることになるのでしょう。
歌舞伎やミュージカルの興行で有名な博多座(はかたざ)とはいわないまでも、能や狂言で人が詰めかける舞台になって欲しいと思うのです。
<こぼれ話>
住吉神社宮司の横田昌和氏によると、こちらの能楽殿では、修復前、年間40回くらい能楽を上演していらっしゃったそうです。
昨年10月にリニューアル柿落としを迎えた際は、九州交響楽団(愛称:九響)の四重奏も披露されました。

能舞台でクラシック音楽というのは、響きが気になるところですが、チェリストの方は「音が床に響いて、とてもいい音色」とおっしゃったそうです。
が、ヴァイオリニストの方は、「空間に音がこもって、気持ちが悪い」とおっしゃったとか。
なるほど、チェロは低音の響きも魅力ですが、ヴァイオリンは、抜けるような高音も大事。周波数が高い高音ほど、演奏者の耳に遅れて到達すると、自分も弾きにくいし、聞いていて気持ちの悪いものかもしれませんね。
ぜひこちらで能楽とクラシック音楽の両方を楽しんでみたいものです!








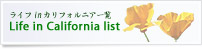
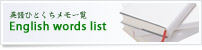
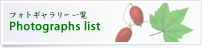

 Page Top
Page Top