色
前回のエッセイ「音」では、日本の夏の音ともいえる、蝉の声のお話をいたしました。
今回は、色のお話をいたしましょうか。
8月の終わり、2週間の滞在を終え日本から戻って来ると、我が家にたどり着いて、まず思ったことがありました。
「光が金色!」
成田から到着したサンフランシスコ空港は、いつもの事ながらちょっと霧がかかっていたのですが、シリコンバレーに南下するにつれてだんだんと霧も晴れ、サンノゼの我が家に着く頃には、あたりはもう太陽の光でいっぱい。そして、見るもの、見るものすべてが金色に輝いて見えるのです。
日本の夏も光線はかなり強いですが、カリフォルニアの光線はなお強い。だから、木々や花々に当たる光が、キラキラと金色(こんじき)に跳ね返って目の中に飛び込んでくるようです。ちょうど、光が物体の上で踊ってでもいるような感じでしょうか。
そして、光はそこら中に充満し、辺りは金色のヴェールに包まれるかのように輝いて見えます。
そこで思ったのですが、いろんな国によって、光の色って違うのだろうなと。
そういえば、アメリカに住み始めて最初に日本に里帰りしたとき、着陸を控える飛行機の窓から見えたのは、深い緑でした。
成田空港のまわりはこんもりとした森の多い所ではありますが、その森の緑は、決してアメリカではお目にかからない類(たぐい)の緑でした。アメリカの緑は、もっとカラカラに乾いた感じとでも言ったらいいのでしょうか。それに比べて、日本の緑はしっとりとしていて深みがある。
祖国を目の前にして、そのように感じたのは、実は、わたしだけではなかったようです。日本画の巨匠である故・東山魁夷(ひがしやま・かいい)画伯は、留学先のドイツから帰国したときのことをこう述べておられます。
「群青(ぐんじょう)と緑青(ろくしょう)の風景だ」と私は思った。「それにしても、なんと可愛らしく、優しく、こぢんまりとまとまっているのだろう」
(中略)
空は晴れていた。海は青かった。しかし、地中海のコバルトやウルトラマリンではなく、白群青(びゃくぐんじょう)や群青という日本画の絵具の色感だった。花崗岩質の島を蔽(おお)う松の茂みは、緑青を塗り重ねた色そのままに見えた。空気は爽やかな中に、潤いと甘やかさを持ち、ほっとするような安らかさと、親しさに満ちていた。
(講談社文芸文庫・現代日本のエッセイ『泉に聴く』より。同書187ページの「東と西 I」を引用。)
これは、昭和10年(1935年)の秋、2年間の欧州滞在を終え、ナポリからの船が瀬戸内海にさしかかったときの印象だそうです。いかにも日本的な風景が、もの珍しく感じられたとも書いておられます。
画伯は、専門の日本画のみならず、文筆にも秀でた方だったので、わたしが初めて里帰りしたときの感覚も、絵具の名を使って的確に表現してくださっているように思います。
そう、日本の色って、外国とはぜんぜん違うんですよね!潤いを含んだ、まったりとした感じ。画伯のおっしゃるように、「ほっとするような安らかさと、親しさに」満ち溢れ、戻って来る者を安堵させる色。
やはり、光というフィルターを通すと、似たような色でも、かなり違って見えるのではないでしょうか?
そして、そんな風に光を感じたのは、日本人だけじゃないんですね。
そう、場所は、遠く離れたフランス。
時は、19世紀末。
登場人物は、絵描きのクロード・モネ(Claude Monet)。
その頃花開いた「印象派」の画家たちは、それまでの絵の技法や決まり事にとらわれず、自分で感じたままを自由に表現した人たちでした。中でも、その中核をなす画家クロード・モネは、「光」をとっても大事にした人でした。
モネは、部屋の中にお行儀よく座るモデルや、机に並べた花瓶や果物ではなく、屋外の自然を好んで題材にしました。風にたなびく草原や、岩場に打ちつける波、そして、勢いよく噴き出す機関車の蒸気と、動きのある景色が彼の心を強くとらえるのです。
わたし自身は行ったことはありませんが、きっと光溢れるフランス南東部のプロヴァンス地方には、彼のお気に入りの景色はたくさんあったことでしょう。
そんな風に自然とじっくりと向かい合う彼は、あるとき、「風景画」というものが存在しないことを悟るのです。
なぜなら、刻々と変わる太陽光線の加減によって、目の前の風景も色を変え、姿を変え、決して制止するものではなかったから。このように、風景とは際限なく存在するものだから、一枚の絵をもってして「これがここの風景です」なんて断言はできないと感じたのですね。
ときに、ふと畑で足を止め、干草の山を描いたことがあります。このときは、2枚のキャンバスを並べ、ほぼ同時に描き始めました。一枚は、日が翳ったときのグレーの絵、そしてもう一枚は、雲が晴れ、辺りが光で満ち溢れているときのカラフルな絵。
そのうち、日が西に傾き、光にオレンジ色が混じるようになります。すると、3枚目のキャンバスを並べ、素早く描き始めます。そう、こちらは、紅(くれない)の夕日に映える干草の山。まるで地平線に落ちる太陽と競争するかのように、筆をリズミカルに運んでいきます。
そんな屋外の経験を積んでいくうちに、光によって姿を豹変する対象物をシリーズ物として描くようになりました。
代表的なものに、寺院(ルーアン大聖堂)や川沿いのポプラ並木などがあります。ルーアン大聖堂は、ブルー、ピンク、黄色といろんな色を基調として、次から次へと30枚も描いたそうです。
そして、睡蓮も。モネというと、まず池に浮かぶ睡蓮の絵を思い浮かべるほどに、お気に入りの題材のひとつだったようですね。
この睡蓮の池は、モネが亡くなるまでの43年間住んでいた、ジヴェルニーの家の向かいにありました。
これはモネ自身がデザインしたもので、もともと湿地帯だった所に付近の川を引き込んで造りました。近くの大工に造らせた日本風の太鼓橋も、なくてはならないアクセントとなっています。自らの手で築いたこの楽園を、彼は何よりも愛していたのかもしれませんね。
チラチラと輝く水面、かぐわしい花を開かせる睡蓮、風にゆらゆらと吹かれる柳の枝と、どれをとっても刻々と変化する題材に、画家としてのチャレンジ精神を駆り立てられていたことでしょう。
このモネという人は、あまりにも光にこだわっていたために、ひとり目の奥さんが病気で死の床にあるときも、彼女の顔に当たる日の光をとらえてみたいと、キャンバスと絵の具を引っ張り出したくらいです。
けれども、それは決して芸術家の奇行などではなく、光によって移りゆく「瞬間」というものを自分の手でとらえたいという、画家の魂の表れなのではないでしょうか。
晩年、モネは、同じく印象派の天才画家で、やはり風景画を好んで描いていたセザンヌと自身を比較し、ふたりの間にはこんな違いがあるのだと説明しています。
「僕たちふたりは、自然を追い求めていたんだ。けれども、彼は自然を(キャンバスの中に)構築して、それをそのまま保存しようとしたのに対し、僕にとっては、一瞬、ただそれだけだった。決して二度と戻らない瞬間を追い求めているんだよ」と。
なるほど、そうやって考えてみれば、景色は光によって刻々と変わるものなんだと、子供の頃から何となく悟っていたような気もしますよね。
夕暮れの頃、家に帰るのも忘れて、辺りの色の変化をボ~ッと眺めていたことがありませんか?それは、やはり、行き過ぎる一瞬一瞬を見逃したくないから、じっとそうやってたんじゃないでしょうか。
誰だって、子供の頃は、光を追う芸術家だったのかもしれませんね。
そして、本物の芸術家は、瞬間を追い求めて、終わりのない旅に出る。なぜなら、自分の芸術には完成などないことを知っているから。
追記: クロード・モネの作品「睡蓮の池と橋」と、当時の池と本人の写真は、ベラジオ美術館(米ネヴァダ州ラスヴェガス)の展覧作品カタログ “The Bellagio Gallery of Fine Art: Impressionist and Modern Masters”(Libby O. Lumpkin, ed., 1998)を撮影させていただきました。
モネの作風については、英BBCが2007年に制作した『Impressionists(印象派の画家たち)』という長編ドラマを参考にいたしました。ドラマ仕立てではありますが、本人たちの書簡やインタビュー、当時の新聞記事などに基づき、史実を忠実に再現しているようです。
蛇足となりますが、モネが最初に絵画学校に入ったとき、クラスメートの中には、後に有名人となるピエール・オーギュスト・ルノワールと、繊細な表現法を持ったフレデリック・バジールがいました。3人はとても仲が良くて互いに励まし合っていたのですが、バジールは29歳の若さで、参戦したプロシアとの戦争で命を落としてしまいます。
モネたち3人組は、少し年長のエドゥアール・マネとエドガー・ドガとも親交を深めていくのですが、やがて、そこに加わったポール・セザンヌを含めて、仲間内の展覧会を開くようになります。これが後に、当時の画壇を牛耳っていたサロンをひっくり返すほどの名声を得て、「印象派」と呼ばれる一派に大成していくのです。
なんでも、「印象派(Impressionism)」という言葉は、第3回の展覧会(1877年)を描写した「印象が薄い(unimpressive)」という辛口の批評からきているんだそうです。それくらい、最初のうちは大不評だったようですね。
それでも、そんな逆境に負けないで、仲間内で切磋琢磨し合った。そして、それが、印象派の画家たちの成長と成功に結び付いたわけですね。学術的な研究もそうだと思いますが、仲間というものは、何か新しいものにチャレンジするときに大きな力を発揮してくれるものなのでしょう。

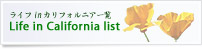
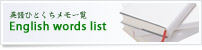
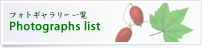

 Page Top
Page Top